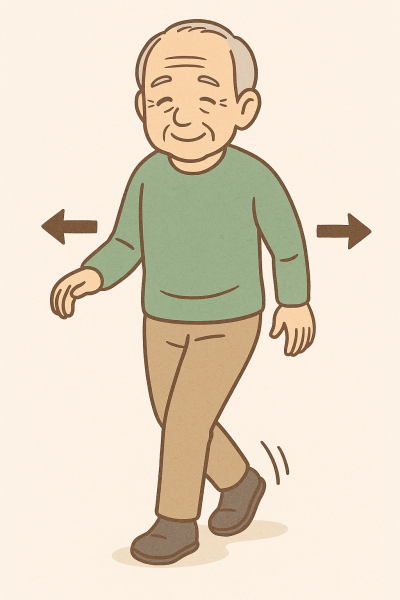“腕を通しにくい”のは“関節の硬さ”より“動きのイメージ”が崩れているサインかも
2025.03.07

“腕を通しにくい”のはなぜ?
〜“関節の硬さ”より“動きのイメージ”が崩れているサインかも〜
—
◆「シャツの袖に腕を通せなくなってきた…?」
・袖口に何度も腕を探る
・一度袖に入っても途中で止まってしまう
・服の向きがわからなくなる
──そんなとき、
「肩が固くなってきたのかな?」「筋力が落ちてる?」と思いがちですが、
実は“動きのイメージ”=運動イメージの変化が原因のこともあります。
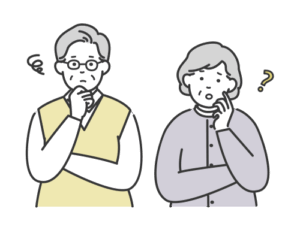
—
◆“イメージできない”と、体も動かない
私たちは普段、
「腕をここに伸ばせば袖に入る」
という動きの“イメージ”を無意識に描きながら行動しています。
しかし、加齢や認知機能の変化によって
・自分の腕の位置や角度がうまくわからない
・袖がどこにあるのかを“空間的に想像”しにくい
・動かす順番がうまく組み立てられない
──こうした“運動のイメージの崩れ”が起こりやすくなるのです。
—
◆“腕が通らない”=“体の地図が曖昧になっている”
・右手で左袖を持っているのに、左腕をうまく入れられない
・腕が服の中で迷子になる
・腕を通したあと、服のどこまで着たかがわからない
──これは“自分の体の位置や動き方”がイメージできていない状態です。
関節や筋力の問題だけではありません。

—
◆支援者ができること
・声かけで“今している動き”を具体的に伝える(例:「左手はここ」「袖を持って」)
・動きの見本を見せる(“見せる支援”はイメージを補います)
・動き出しを一緒にサポートし、途中は任せる
・袖口にわかりやすい目印や質感の違いを工夫しておく
“できる動作”ではなく“わかりやすい動作”をつくることが大切です。
—
◆まとめ
・“腕が通らない”のは、筋力や柔軟性だけが原因とは限らない
・“動作のイメージ”の崩れが、身体の動きを迷わせている
・少しの声かけや工夫で、“通せた”という体験が積み重なる
うまくできないその動きに、脳の混乱が隠れているかもしれません。
焦らず、ひとつずつ“動きの地図”を取り戻していきましょう。