“トイレを我慢するクセ”が、歩行機能を下げる理由
2024.11.01

“トイレを我慢するクセ”が、歩行機能を下げる理由
〜排泄行動は、“移動”と“判断”の連続トレーニング〜
—
◆「あとで行こう」と思っているうちに…
・トイレに行きたいのに、なんとなく後回し
・「今は人がいるから…」「あとでまとめて…」
・結局ギリギリになって慌てて動く
──こうした“トイレを我慢する習慣”が、
歩く力・立ち上がる力・判断力を少しずつ低下させていることがあります。
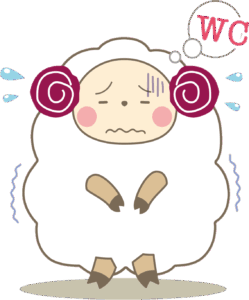
—
◆トイレ動作は“最高の応用歩行”
・尿意や便意を感じて判断する
・立ち上がって移動する
・服を脱ぐ・姿勢を保つ・排泄・立ち上がる
これらはすべて、短時間のうちに複数の機能を組み合わせた動作です。
つまり、トイレに行く=毎回が“実践的なリハビリ”になっているのです。

—
◆我慢が“動き出しの遅れ”をつくる
・「ちょっと面倒だな」という心理
・「間に合うかな」という不安
・「今じゃなくていい」という判断の先送り
これが繰り返されることで、
歩き出すタイミングや判断のスピードが鈍くなり、
“動こうとするきっかけ”そのものが減っていきます。
—
◆“すぐ行く”習慣がもたらす効果
・“歩く頻度”が自然と増える
・立ち上がる動作のトレーニングになる
・「自分でできた」という自己効力感が得られる
・転倒リスクの高い“ギリギリ行動”を防げる
「尿意=行動スイッチ」として捉えると、日常にリズムが生まれます。

—
◆まとめ
・“トイレを我慢するクセ”は、歩行や判断力の低下につながることがある
・トイレ動作は、実は“最高の生活リハビリ”
・「行こうかな」と思った瞬間が、“機能を保つチャンス”
あなたの歩く力は、今日の1回のトイレ行動でもう一度育て直せます。


















