“家での介助”がつらいときに読む話〜“頑張らない介助”の考え方〜
2025.10.03

“家での介助”がつらいときに読む話
〜“頑張らない介助”の考え方〜
—
◆「家での介護がつらい」と感じるのは、あなただけではありません
「私がしっかりしなきゃ…」
「家族だから、弱音を吐いたらいけない…」
そんなふうに、知らず知らずのうちに自分を追い詰めていませんか?
在宅介護の現場では、多くのご家族が“ひとりで頑張りすぎる”傾向にあります。
しかしその“責任感の強さ”こそが、心と体をじわじわと疲弊させてしまうのです。
—
◆「つらい」と思ったときが、“頑張りすぎ”のサイン
以下のようなサインが出ていたら、それは“赤信号”です。
・介助中にイライラしやすくなった
・相手の言動に傷つきやすくなった
・介助が終わったあと、涙が出そうになる
・夜に眠れず、食欲も落ちてきた
これらは「燃え尽き症候群(介護バーンアウト)」の初期症状ともいわれ、
放っておくと心身の不調へとつながることもあります。
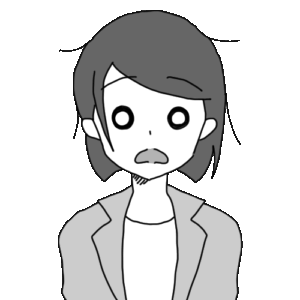
—
◆“頑張らない介助”とは?
“頑張らない介助”とは、「手を抜く」ことではなく、
「手を貸しすぎないこと」「適度な距離を保つこと」「頼れるものを使うこと」です。
1. 自立を尊重する
→「できること」は見守り、「できないこと」だけを手伝う
2. 道具に頼る
→介護ベッド、滑りやすいシート、手すりなどを上手に使う
3. 外部サービスを使う
→訪問リハビリ、デイサービス、ショートステイなどを積極的に活用
4. 家族以外と分担する
→ケアマネジャーや医療スタッフと“相談”しながら負担を軽減する
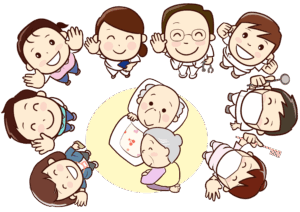
—
◆介護の中に“心のゆとり”を
心の余裕がないと、介助される側にも「申し訳なさ」「気まずさ」が生まれてしまいます。
一方で、介助する側が「無理のないスタンス」で関わると、
お互いにとって心地よい距離感が保たれます。
“介助される”ことに慣れていない高齢者ほど、
「ありがとう」よりも「迷惑かけてごめんね」と言いがちです。
そのときこそ、こう伝えてみてください。
「無理してないから大丈夫。
できるときに、できることを一緒にやっていこうね」
—
◆「介護=無理をすること」ではない
介護のゴールは、“すべてをこなすこと”ではなく、
“長く続けていけること”です。
そのためには、頑張ることよりも「ゆるめること」が必要なときがあります。
“あなたの余裕”が、相手の安心を生みます。
一緒に暮らすためにこそ、「頑張らない介助」の視点を持ってみてください。
—
◆まとめ
・「つらい」と感じたときは“サイン”に気づくことが大切
・“頑張らない介助”とは、相手のためにも自分のためにもなる優しい方法
・道具・サービス・人の手を借りて、“続けられる介助”を目指そう
介護は、“完璧じゃなくていい”。
だからこそ、今日から“力を抜いて”みませんか?



















